読解問題の校閲力テスト◆国語教材の執筆者・校正者向け
以下は高校の国語テストを想定して作った出来損ないの設問です。
解き直し校正を行い、再考・修正すべき問題点を簡潔に指摘してください。
■指摘の例
ほかにもあるかもしれませんが、とりあえずこの3点は指摘したいところです。
仮にこれが正答として成立しているとするならば、高校の設問としては簡単すぎるという点を指摘することもできるでしょう。
一見、設問と対応しているかのような2については、慌てているとスルーしてしまうことがあるので要注意。
この解答に必要な要素は、「災がつづいた」→「洛中がひどくさびれ、羅生門の修理を顧みる余裕などない」→「荒れ果てて、ついには死人が棄てられるようになった」→「気味悪るがって誰も足をふみ入れなくなった」ですから、これらのポイントをまとめなければ解答として成立しません。
もしこれらの一部のみを答えさせたいのであれば、解答が絞り込めるような設問文に変える必要があります。(その場合でも、この解答は易しすぎるため、やはり使えませんが。)
3については、「ケイの前にほぼ同じフレーズがありますよ」ということを、簡潔に指摘できていればOKです。
なお、このような1題で複数の難点を抱えている設問は、現場でもよく見られます。
おかしいと感じる点があれば、(冗長にならないよう注意しながら)すべて伝えたほうがよいでしょう。
校閲スキルをアピールできますし、何より改題する編集者への有益なガイダンスになります。
見落としやその他の重要な問題点がありましたらお知らせください。(自分で作った問題を校正しているため、客観視するのが困難です。)
解き直し校正を行い、再考・修正すべき問題点を簡潔に指摘してください。
次の文章を読み、あとの問いに答えよ。
ある日の暮方の事である。一人の下人(げにん)が、羅生門(らしょうもん)の下で雨やみを待っていた。問 傍線部「この男のほかには誰もいない」のはなぜか、45字以内で答えよ。 |
| 解答 <例>この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつづいて起ったから。(41字) |
全力で吟味してから校閲例をご覧ください。
校閲例を見る
■指摘の例
- 解答が本文のほぼ抜き出しになっており、自由記述の意味をなしていない。
- 解答の内容が設問に対して不十分である(飛躍している)。
- 設問をママにするなら、初出(同段落冒頭)の「この男のほかに誰もいない」に傍線位置を移動する?
ほかにもあるかもしれませんが、とりあえずこの3点は指摘したいところです。
仮にこれが正答として成立しているとするならば、高校の設問としては簡単すぎるという点を指摘することもできるでしょう。
一見、設問と対応しているかのような2については、慌てているとスルーしてしまうことがあるので要注意。
この解答に必要な要素は、「災がつづいた」→「洛中がひどくさびれ、羅生門の修理を顧みる余裕などない」→「荒れ果てて、ついには死人が棄てられるようになった」→「気味悪るがって誰も足をふみ入れなくなった」ですから、これらのポイントをまとめなければ解答として成立しません。
もしこれらの一部のみを答えさせたいのであれば、解答が絞り込めるような設問文に変える必要があります。(その場合でも、この解答は易しすぎるため、やはり使えませんが。)
3については、「ケイの前にほぼ同じフレーズがありますよ」ということを、簡潔に指摘できていればOKです。
なお、このような1題で複数の難点を抱えている設問は、現場でもよく見られます。
おかしいと感じる点があれば、(冗長にならないよう注意しながら)すべて伝えたほうがよいでしょう。
校閲スキルをアピールできますし、何より改題する編集者への有益なガイダンスになります。
見落としやその他の重要な問題点がありましたらお知らせください。(自分で作った問題を校正しているため、客観視するのが困難です。)
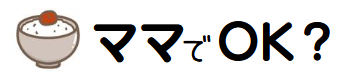

 以下は高校の国語テストを想定して作った出来損ないの設問です。
以下は高校の国語テストを想定して作った出来損ないの設問です。